
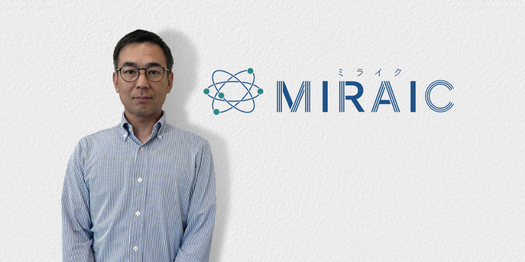
投稿日:
インタビュー近年、デジタル化の波を受けて、人事評価制度のクラウド化が広がっています。しかし、単なるシステム導入だけでは解決できない課題も多く、真に組織の成長と社員の育成につながる仕組みづくりが求められています。
そこで今回は「人が育つ組織を育てる」をコンセプトとした人事評価・育成システム『MIRAIC(ミライク)』を運営する株式会社みらいの人事、代表取締役の藤崎さんに、人事評価制度の構築から運用定着までや、人事評価を組織文化に変える取り組みなどについてお話をお伺いしました。
目次
—まず初めに『MIRAIC(ミライク)』というサービスが生まれた背景について教えてください。どのような課題意識や現場の声が、開発のきっかけとなったのでしょうか?
藤崎さん
弊グループは、中堅・中小企業に向けて、人事制度のコンサルティングをご支援しています。そのなかで「中堅・中小企業が使いやすく、本当に必要な機能を搭載したシンプルな人事評価システムを提供できないだろうか」と考えたことが、このサービスを開発するきっかけとなりました。
—いわゆる“人事評価制度のクラウド化”は近年多くの企業で進んでいますが、『MIRAIC』ならではの設計思想や、他と一線を画すポイントがあれば教えてください。
藤崎さん
『MIRAIC』は「人が育つ組織を育てる人事評価・育成システム」です。単なる人事評価機能だけでなく、上司と部下との間の信頼関係やコミュニケーションの量と質を高めるための機能を備えている点が特徴です。
—人事評価システムというとつい数値化や効率化に目が向きがちですが、根本的な人と人との関係性を重視されているということですね。
藤崎さん
納得感のある評価結果や、成長や育成につなげられるような評価運用には上司と部下との間の信頼関係・コミュニケーションの量と質が必須だと、ご支援事例を通じて感じているからこそ、1on1機能とココロの共有機能(日々の業務を通じた経験を上司と内省する機能)を『MIRAIC』に設けています。
—中小企業において、人事評価や育成制度の整備は後回しになりがちです。そうした企業が制度構築に踏み出すきっかけとして、何が重要だと思われますか?
藤崎さん
人事評価や育成の整備に早く取り組むことで、現場の負担減少や成果向上につながる可能性をふまえて制度構築の優先度を再考することが重要だと思います。
既存社員の定着・更なる戦力化を促進する環境を整えなければ、「ヒト」の課題に直面しやすくなります。採用難の状況も加味し、気づいたときには遅い、という事態を避けるために、制度構築に踏み出す時期をご検討いただくことをおすすめします。

—実際に御社へ相談が来る企業の声を聞くなかで、特に印象に残っているエピソードや課題などがあればご紹介いただけますか?
藤崎さん
最初は「評価事務に手間がかかっている」という課題を伺うことが多いのですが、お話を進めるうちに、
など、システム導入だけでは解決できない課題が浮き彫りになるケースが比較的多いことが印象的です。弊グループはコンサルティング会社としてシステムを扱っているため、このようなご相談も大歓迎です。
—「評価制度を変える=会社の文化を変える」ことにも繋がると思います。導入初期に企業側で特に意識すべき点はどんなことでしょうか?
藤崎さん
適切な評価運用をし続ける文化をつくることです。せっかく構築した新たな人事評価制度が、働きやすさ・働きがい・成果につながる良い意味での会社の文化の変化を生むか、不公平や不満・面倒くささの温床になるかのカギは、人事評価制度をどう運用するかにあると考えています。
確実に公平で納得感のある評価を実現する魔法のような人事評価制度は、存在しません。制度に込めた会社のメッセージを正しく社員に伝えながら、上司と部下との間の信頼関係やコミュニケーションの量と質を積み上げ続ける“泥臭い”運用を徹底する必要性を意識していただくことが重要です。
—『MIRAIC』を利用し始めた企業が、導入初期に“つまずきやすい”ポイントや誤解しやすい部分があれば教えてください。
藤崎さん
「人事評価システムを導入すれば評価運用がうまく回る」とは限らない点です。人事評価機能だけをご導入いただいた場合、評価事務の効率化は実現できても、評価結果への納得感が薄い、社員が評価運用に向き合わないなどの課題が残るケースがあります。
「人事評価システムを探しているため、
—運用が定着し、効果が見え始めるまでには、どれくらいの期間やフェーズがあると見ていますか?また、どんな変化が最初に現れますか?

藤崎さん
操作や運用方法については、いつでも人事コンサルがサポートしますので、評価事務の効率化は比較的早く効果を実感いただけるケースが多いです。一方で、納得感のある評価結果を得て成長や育成につなげるには、ココロの共有などの機能を活用し、社員と年単位で取り組みを継続することが必要です。最初の変化としては、これまで知らなかった部下や社員の考えに気づく場面が多く見られます。
—コスト面で導入を躊躇している企業にも“まずやってみよう”と伝えたい、実践的な工夫や低コストな始め方などがあれば教えてください。
藤崎さん
システム利用料はリーズナブルに設定しています。まずは、評価事務の効率化や上司と部下との間のコミュニケーションの習慣づけを目的に、システムを導入してみてください。
—もし可能であれば『MIRAIC』導入企業のなかで、特に成功事例として印象的なケースがあれば紹介いただけますか?
藤崎さん
人事評価機能だけを導入する企業も多いですが、大きな効果を得ているのは、ココロの共有などの機能も併せて導入し、運用を徹底している企業です。ある企業では、
との声がありました。今では「不満をもちやすい社員が前向きになった」「会議で発言が増えた」と組織風土の変化まで感じられています。
—その企業がうまくいった具体的な要因は何だと考えますか?
藤崎さん
ココロの共有を運用するには一定の労力がかかりますが、それを必要な時間として運用を徹底したことだと考えております。
—これから人事評価制度の見直しに取り組もうとしている企業に対し、「まずこれだけは押さえておいてほしい」と思うポイントがあれば教えてください。
藤崎さん
自社が運用し続けられる制度にすることです。当たり前のように思われるかもしれませんが、人事評価制度を設計し始めると、精緻にしようと細かくしすぎることがよくあります。結果的に運用負担の重い複雑な制度にしてしまうと、制度が形骸化し、制度見直しをおこなった意味がなくなるリスクがあります。自社に合った制度を作りつつ、運用負担とのバランスを意識してください。
—『MIRAIC』をより深く活用していくうえで、企業側が主体的に取り組むべきステップや意識変化についてアドバイスがあればお願いします。
藤崎さん
評価事務の効率化だけでなく、ココロの共有などの活用にもぜひ目を向けていただきたいです。上司と部下との間の信頼関係の醸成・成長や育成の促進のための取り組みも並行しておこなうことで、評価運用にも組織にもより良い変化を生み出せます。
—人事労務の分野において、今後どのような変化やニーズの高まりを感じておられますか?また、御社として取り組んでいきたい今後の展望があれば教えてください。
藤崎さん
「ヒト」に関するご相談は非常に増えています。転職が一般的になり、制度や条件といった“ハード面”だけでなく、働く意味を感じられる“ソフト面”の価値も重要性が高まっています。弊グループは“ハード面”はもちろん、ココロの共有などを通じた“ソフト面”へのご支援にもより注力していきたいと考えています。
—最後に『MIRAIC』の活用を通じて、“人と組織”の可能性を広げたいと考える企業に向けて、メッセージをお願いします。
藤崎さん
本記事に少しでも興味をもたれましたら、ぜひ一度ご相談ください。貴社に合った人事評価や育成の運用を、一緒に考えさせていただきます。

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
詳しいプロフィールはこちら