この記事でわかること・結論
- 103万円の壁とは、所得税の支払い義務が発生するボーダーラインのこと
- 2025年から103万円の壁は最大160万円まで引き上げられることが決まっている
- 160万円の壁では、年収ごとに基礎控除の上乗せ額が設定され、年収が低い人ほど控除額は大きくなる
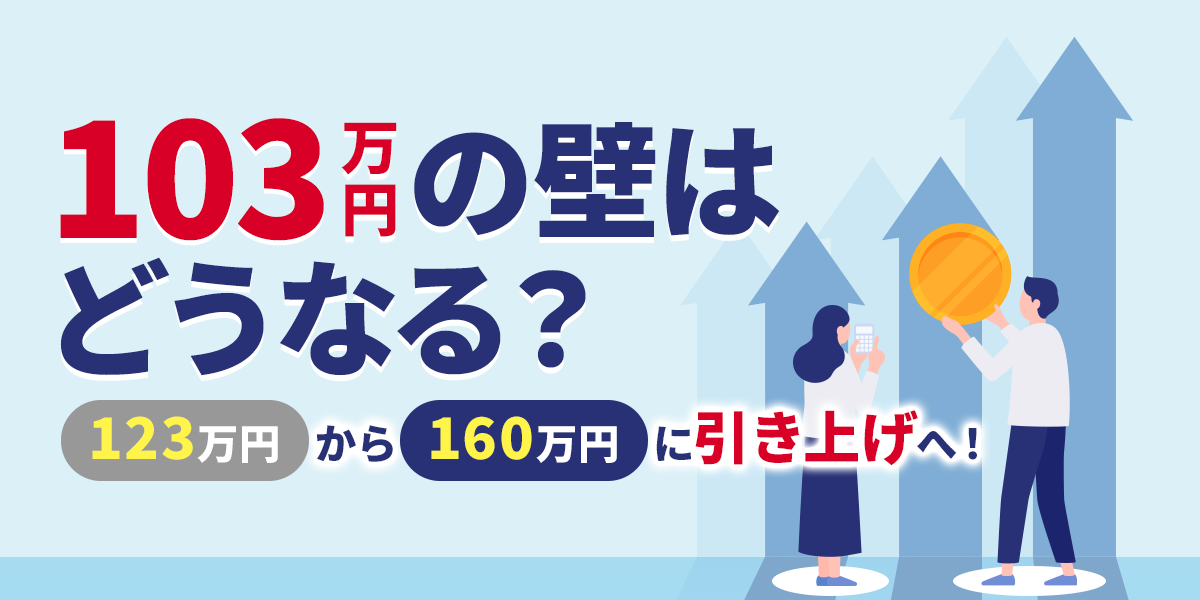
更新日:
ニュースこの記事でわかること・結論
長らく議論されていた「103万円の壁」問題に、ついに決着がつきました。2025年3月、2025年予算案が衆議院を通過し、103万円の壁は最大160万円まで引き上げられることが決定しました。
これまでに「123万円の壁になる」「178万円まで引き上げられる」などとさまざまな法案が出ていましたが、なぜ160万円に決まったのでしょうか。
この記事では、160万円の壁決定までの経緯と160万円の壁のしくみ、160万円への引き上げでいくら手取りが増えるのかなどをわかりやすく解説します。
目次
2024年の年末から議論が続いていた「年収103万円の壁」問題。与野党の攻防が続いていましたが、2025年3月4日におこなわれた衆議院の本会議にて自民・公明党・日本維新の会の賛成により、2025年予算案がついに決定されました。
103万円の壁に関しては、与党が提案した「年収に応じて非課税枠を最大160万円まで引き上げる」法案が衆議院を通過しました。
103万円の壁とは、所得税の支払い義務が発生するボーダーラインのことです。パートタイムやアルバイトとして働く人は、この壁を超えないように、働く日数や時間を減らす”働き控え”をおこなうケースが多く見られており、人手不足の要因の一つと言われています。
実際、当サイトが年収103万円以下の300名を対象におこなったアンケート調査において、年収103万円を超えないように働く時間や日数を控えたことが「ある」と回答した方は74.7%にのぼり、多くの方が年収の壁を超えないように働く時間や日数を調整している現状が明らかとなりました。

少子高齢化によって労働人口の減少が進む日本において、働き控えによってさらに労働人口が減ってしまうことは、大きな問題です。このような背景があり、103万円の壁の引き上げに関する議論が続いていました。
2024年末時点では、基礎控除と給与所得控除をそれぞれ10万円引き上げ、103万円の壁は「123万円の壁」に、加えて、年収850万円以下の給与所得者を対象に減税措置がおこなわれる見通しでした。

しかし、この法案に国民民主党から「基礎控除の引き上げは憲法で定める生存権に基づくべき」と主張があったため、自公両党は、東京都の生活保護基準や最低賃金の水準などを考慮し、年収200万円以下の低所得層の税負担を軽減するために控除額を最大160万円まで引き上げることを決めました。
160万円の壁のポイントは「年収に応じて非課税枠が引き上げられる」点です。年収ごとに基礎控除の上乗せ額が設定され、年収が低い人ほど控除額は大きくなります。

現在の103万円の壁では、年収103万円以下であれば所得税がかからない(基礎控除は48万円)とシンプルです。しかし160万円の壁では、年収によって基礎控除が決まり、所得税がかからないラインが160万円まで引き上げられるのは、年収200万円以下の給与所得者となります。
国民民主党の玉木代表はこれについて「控除額が160万円まで引き上がるのは全体の5%弱である」と批判しています。
なお具体的な基礎控除は、年収200万円以下なら95万円、年収475万円以下なら88万円、年収665万円以下なら68万円、年収850万円以下なら63万円です。2024年末時点で決定していた「123万円の壁」案から比較すると、基礎控除は5万円~37万円上乗せされることになります。
| 年収 | 基礎控除 |
|---|---|
| 200万円以下 | 95万円 |
| 475万円以下 | 88万円 |
| 665万円以下 | 68万円 |
| 850万円以下 | 63万円 |
ただし、年収200万円から850万円までの給与所得者の場合、上記の上乗せされる基礎控除は2年間(2025年と2026年)限定です。
その理由として与党は、年収200万円から850万円までの給与所得者に対する基礎控除の上乗せは「賃金の上昇が物価の上昇に追いつくまでの措置」と説明しています。現時点で財源の目途がつく2年間限定とし、もし継続する必要があれば恒久財源を改めて探すとしています。
国民民主党は年収103万円の壁問題において「手取りを増やす」といったキャッチフレーズのもと、178万円までの引き上げを主張してきました。しかし今回、160万円の壁になることが決定し、178万円には至りませんでした。
そこで気になるのが『103万円の壁が160万円の壁になることでいくら手取りが増えるのか』ということです。ここからは、160万円の壁に改正された後の手取り試算を見ていきます。
以下は、103万円の壁が「今回の与党案の160万円の壁になった場合」と「国民民主党案の178万円の壁になった場合」における年間の減税額の試算です。中学生以下の子供が一人いる家庭(妻は専業主婦で配偶者控除あり)で給与所得控除分も含まれています。
| 年収 | 160万円の壁 | 178万円の壁 |
|---|---|---|
| 300万円 | 2万円 | 11万1,000円 |
| 500万円 | 1万円 | 11万3,000円 |
| 800万円 | 3万1,000円 | 22万7,000円 |
| 1000万円 | 2万円 | 22万8,000円 |
| 1500万円 | 3万4,000円 | 32万8,000円 |
上記のとおり、今回決定した160万円の壁では年間で1万円~3万円程度しか手取りは増えません。国民民主党案と比較すると、年間で約5倍~10倍の差が出ています。
第一生命経済研究所の試算によります。
試算結果だけを見ると国民民主党が提案した178万円が、多くの人の手取りを増やすには有効に思えますが、178万円までの引き上げについて争点となったのはその”財源”です。財源をどうするのかの議論が長らく続けられた結果、今回の160万円案に決まりました。
なお、所得税の非課税枠が最大160万円まで引き上げられることによる減税額は、1兆2,000億円と言われています。103万円の壁が決定された1995年と比べて現在の物価上昇率は10%であることから、この減税額は少ないといった指摘もあり、石破総理は「178万円を目指すということについても考えが変わったわけではない」と今後も議論は続く考えを示しています。※2025年12月18日の政府・与党合意により、2026年度から178万円に引き上げられる見込み
103万円の壁見直しへの対応は企業規模にかかわらず重要ですが、特に中小企業にとっては、人材確保や経営戦略に大きな影響を与える可能性があります。 ここからは、中小企業の人事・労務担当者が取るべき対応策を解説します。
103万円の壁の引き上げにより、従業員の所定労働時間が増えたり、社会保険への加入条件が変わったりする場合があります。そのため、雇用契約を見直す必要があります。
| 人事・労務担当者の対応 | |
|---|---|
| 労働時間・ 時間外労働 |
従業員の希望や業務内容に合わせて、労働時間や時間外労働について見直す |
| 賃金 | 労働時間や業務内容に合わせて適切な賃金を設定する |
| 社会保険 | 社会保険の加入条件を満たす従業員がいる場合は加入手続きをおこなう |
| 雇用契約書の作成 | 変更点を明確に記載した雇用契約書を作成し、従業員に提示する |
労働時間が増えることで、社会保険への加入義務が発生する場合もあります。手続きを怠ると、行政機関から指導や罰則を受ける可能性もあるため、速やかに対応しましょう。
配偶者手当の支給条件に収入制限を設けている場合は、配偶者手当の見直しを検討しましょう。配偶者の収入制限を設けていると、配偶者が働く時間を制限したり、働くことを諦めたりしてしまう可能性があります。
収入制限を撤廃する、または配偶者の有無にかかわらず公平に賃金を評価するしくみを導入することで、配偶者が制約を受けずに働ける環境を整えられます。配偶者手当の見直しは、従業員のモチベーション向上や、人材活用の促進にもつながります。
103万円の壁が引き上げられることにより、労働者が非課税で働ける時間が増え、手取り収入が増加します。 これにより、従業員の働く意欲が向上し、企業にとっては優秀な人材を確保しやすくなるというメリットがありますが、その一方で、人件費が増加するというデメリットも生じます。
特に中小企業では、急激なコスト増が資金繰りに影響をおよぼす可能性があるため、事前に資金計画を見直すことが重要です。
| 人事・労務担当者の対応 | |
|---|---|
| 資金繰り表の作成 | 現状の資金繰りを把握し、将来の資金繰りを予測する |
| コスト削減 | 無駄なコストを削減し、利益を確保する |
| 資金調達 | 必要に応じて、融資や助成金などの資金調達を検討する |
必要な資金を確保し適切な資金管理をおこなうことで、人件費増加に柔軟に対応し、事業運営の安定を保てます。
1995年から変わっていなかった103万円の壁が、2025年に最大160万円まで引き上げられることが決まりました。2025年から所得税の控除額が160万円まで引き上げられるのは年収200万円以下の給与所得者のみであり、年収200万円から850万円までの給与所得者は、2年間限定で基礎控除が上乗せされます。
国民民主党が提案していた「178万円までの引き上げ」の実現には至りませんでしたが、今後も年収の壁問題は178万円を目標に議論が続く見込みです。
そして103万円の壁見直しに伴い、労働時間を増やすパート・アルバイト従業員も出てくるでしょう。企業の人事・労務担当者は雇用契約の見直しや社会保険の加入手続きなど、適切な対応が求められます。

平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を行う。
退職時におけるトラブル相談や、転職時のアドバイスなど、労働者側からの相談にも対応し、労使双方が円滑に働ける環境作りに努めている。
また、近時は活動の場をWeb上にも広げ、記事執筆や監修などを通し、精力的に情報発信を行っている。